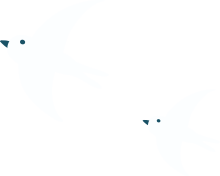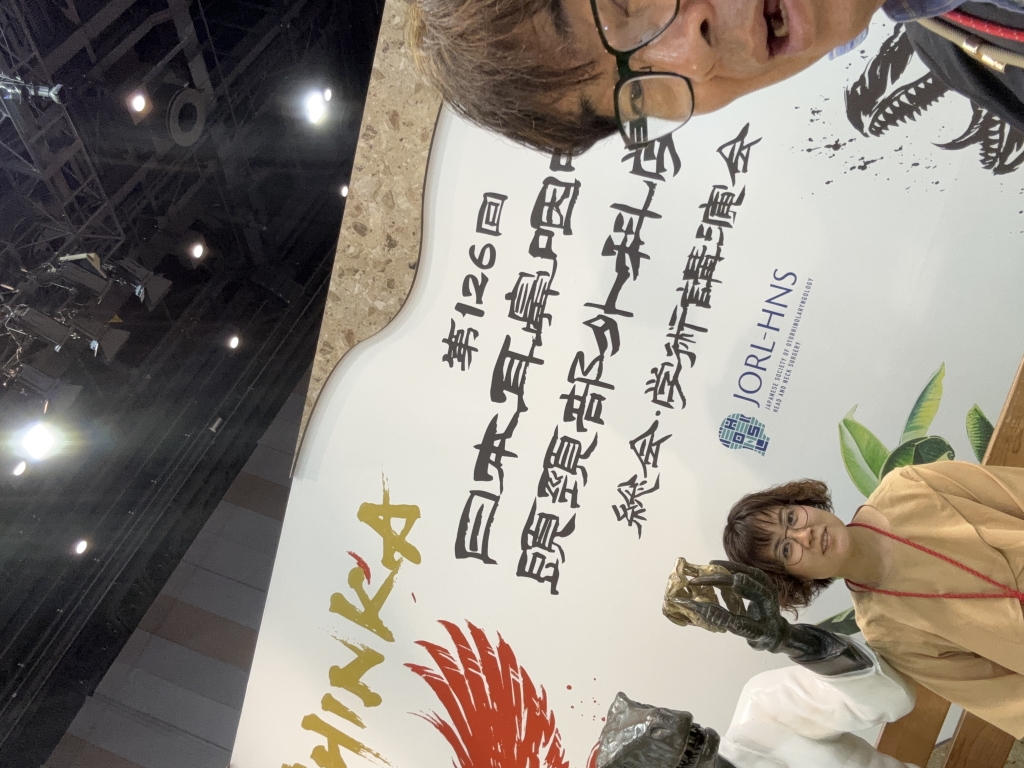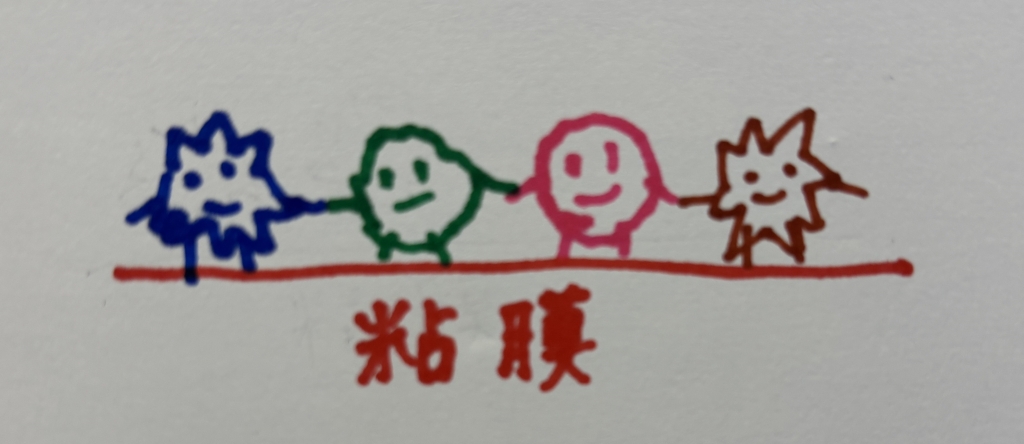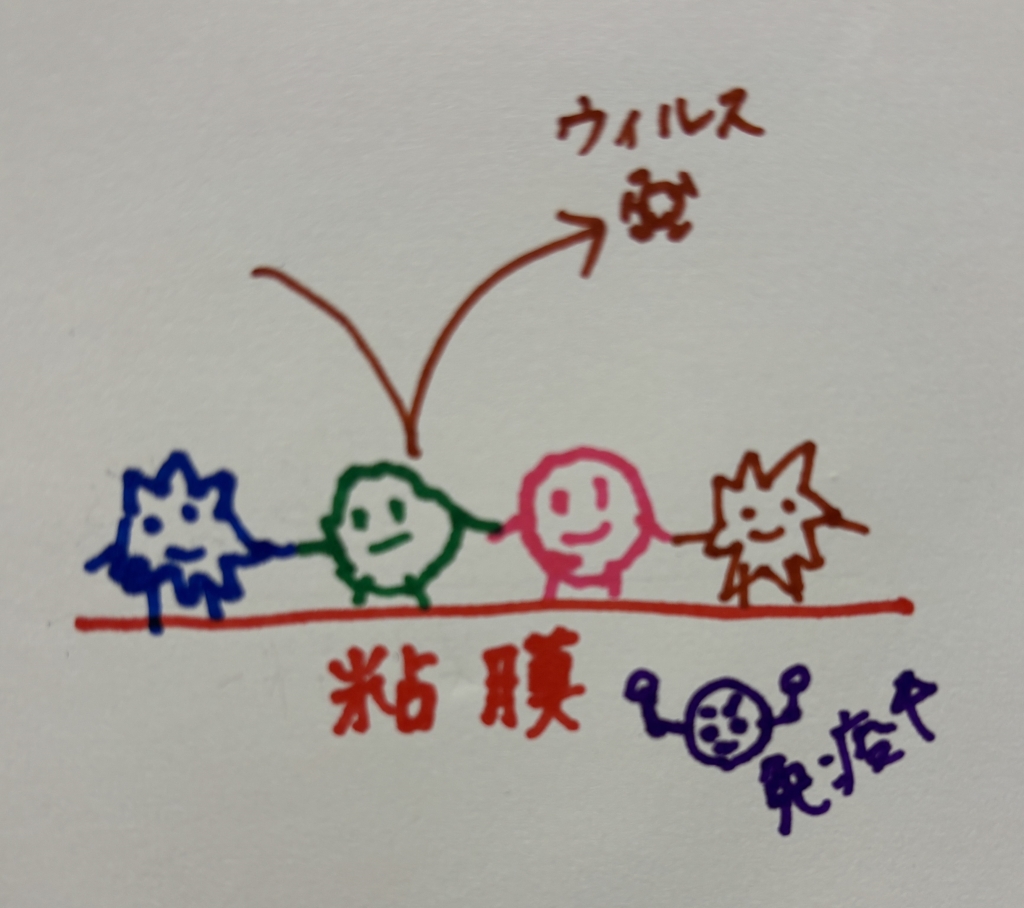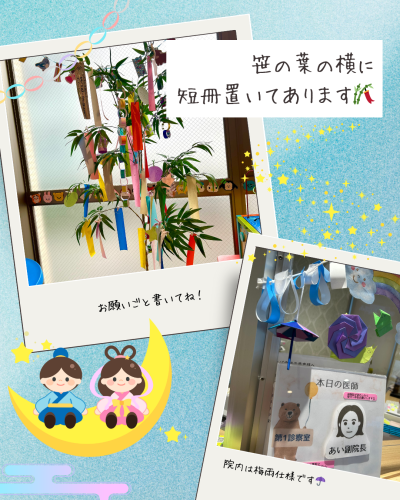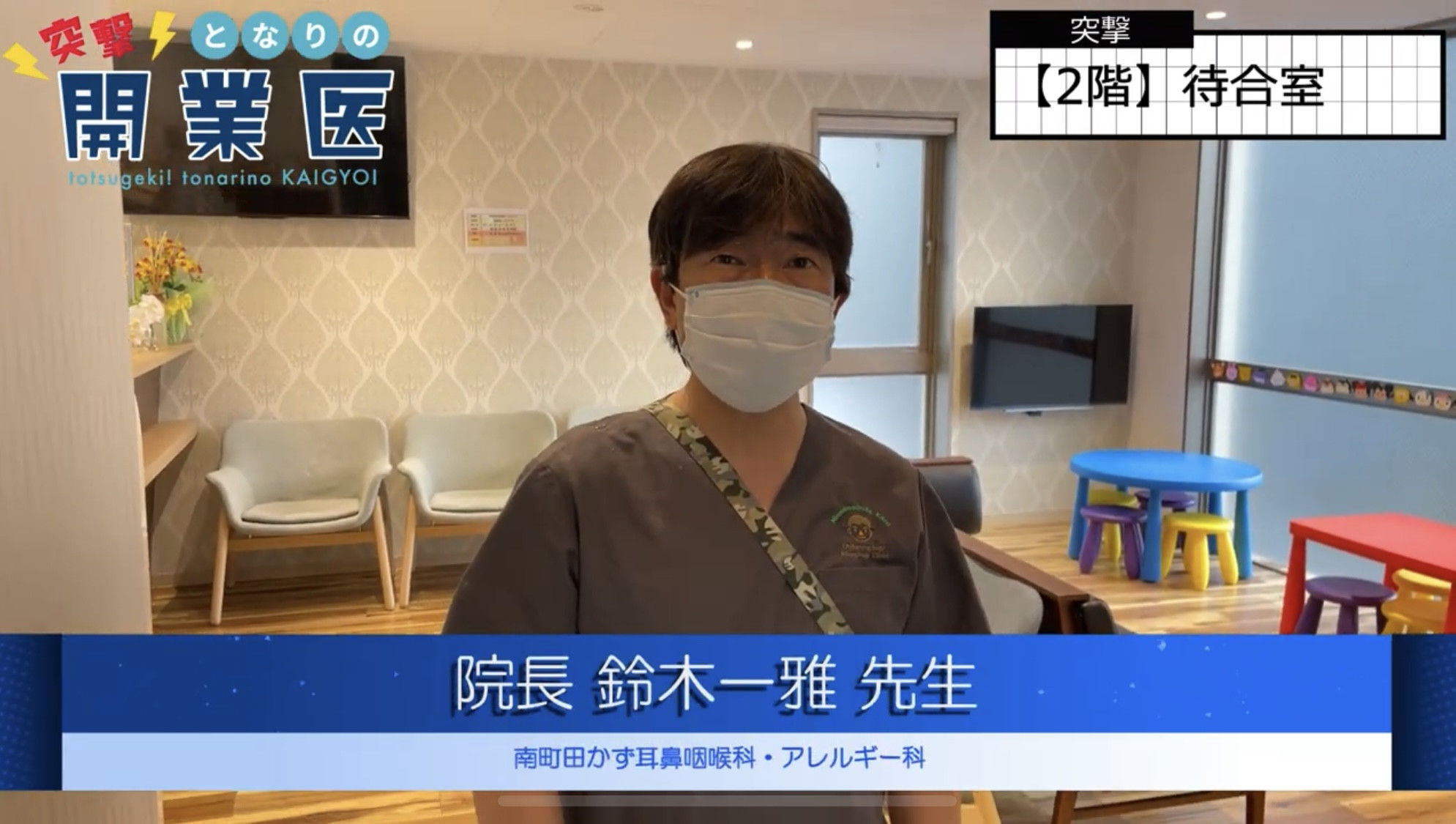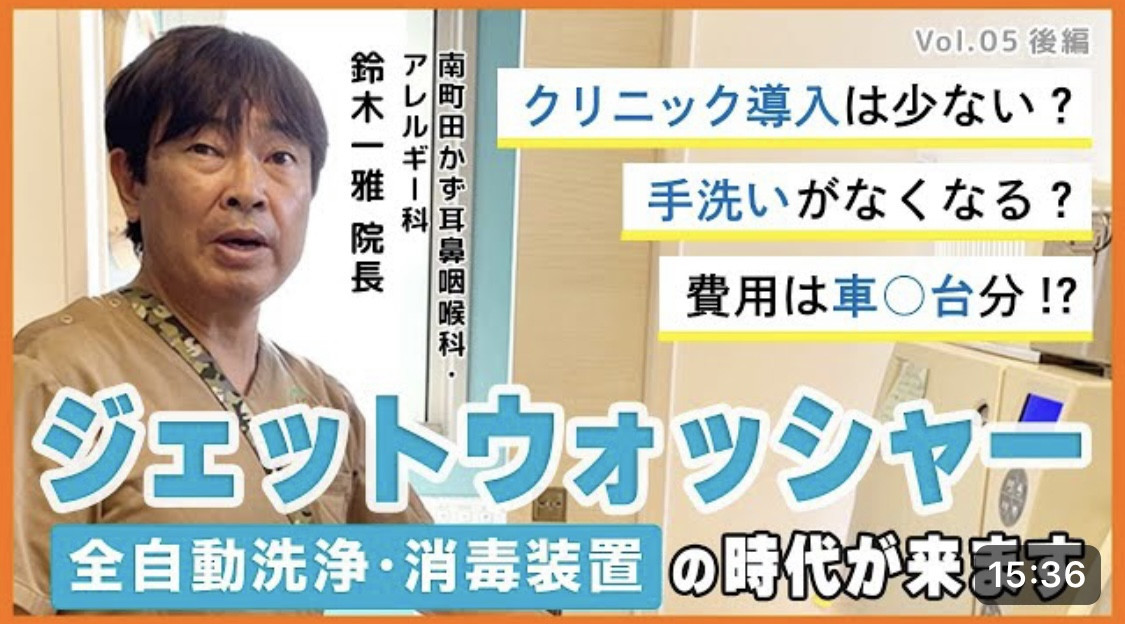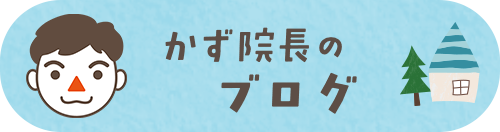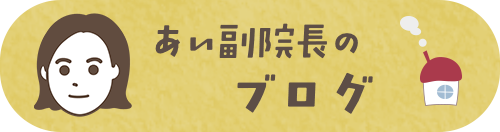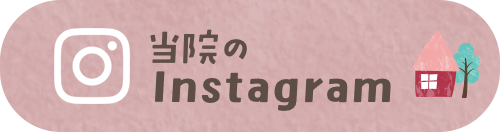ブログ
あい先生のブログから 抗生剤のデメリット②
アレルギー疾患にかかりやすくなる
「2歳までに抗生剤を使ったことがあると、その後気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎になる確率が上がる」
という報告があります。
抗生剤で常在菌をやっつけてしまうせいで、免疫システムに異常を引き起こすためだといわれています。
(アレルギー疾患というのは自分の免疫が自分を攻撃してしまうことで起こる病気です。抗生剤で免疫が本来戦うべき相手をやっつけてしまうと、戦う相手がいなくなって手持無沙汰になってしまった免疫が自分を攻撃してまうのかな、とも思っています。←私見です。)
でもですね、私のこどもたちには3人とも抗生剤を使いませんでしたが、3人ともアレルギー検査をすると結構陽性にでるんですよ!!
でもまあ、その割には症状があんまりなく、抗アレルギーを常用するほどではないのは、抗生剤を使わなかったおかげなのかどうなのか、、わかりません。
免疫の成長を妨げる(私見です)
幼少時はよく鼻風邪をひきます。
その場合、鼻の風邪薬を処方して経過をみます。
鼻の風邪薬とは、ムコダイン(カルボシステイン)、ムコソルバン(アンブロキソール)のことです。
粘っこくなった鼻水の粘り気をとって、鼻水を出しやすくすることで、鼻詰まりを楽にします。
しかし、これらの薬で症状がピタッと治るわけではありません。
治るには自分の免疫細胞が頑張る必要があります。
こどもの免疫細胞はまだまだ未熟なので、なかなか自力で治すことができず、何週間も鼻がグズグズしていまうことも多いです。
だけどそうやって免疫細胞がウィルスや細菌をやっつける練習をして、少しずつ免疫が成長するのだと思っています。
話はかわりますが、コロナ禍があけて、マスク&徹底除菌の生活から解放されたと同時に、風邪ひきの患者さんが多く受診されました。よく風邪をひくだけでなく、こじらせてなかなか治らない方が異様に多かった記憶があります。マスク&徹底除菌生活でウィルスや細菌にふれる機会がへったせいで、免疫が落ちているんだろうな、と思いました。
「いざ、鎌倉!」ではありませんが、戦いに備えて普段から訓練を積んでおくことが大切なのだと痛感しました。
話は戻って、
成長過程のこどもなら、尚更。
ウィルスや細菌と戦う訓練を沢山して、免疫を強くしてほしいです。
抗生剤を使うということは、免疫の成長の機会を奪うということです。
ですので、私は急性中耳炎にならないかぎりは、鼻風邪を多少こじらせても抗生剤は処方しません。
時々「副鼻腔炎になっていませんか?」と聞かれますが、幼少期は副鼻腔がまだしっかり発達していないので、大人のようにこじらせた副鼻腔炎になることはありません。大人のこじらせた副鼻腔炎には抗生剤が必要なことが多いので、親御さんが心配するのですね。乳幼児の場合は、鼻風邪はこじらせてもあくまで鼻風邪です。
「鼻が垂れていても元気なら、ヨシ!」と思っています。
それでも親御さんから「そうはいっても、もう何週間も鼻を垂らしていてかわいそうなので、抗生剤をください」といわれることがあります。
その場合は処方します。
けれど、面と向かってはいえないのですが、心の中でこう思っています。
抗生剤を飲ませる前に、やれることがありますよー、と。
なにをするかというと、免疫のパフォーマンスをあげるために、しっかり休ませることです。
もちろん、保育園を休ませることではありません。
夜、普段より早めに寝かせたり、休日、おうちでゆっくり過ごしたり、といったことです。
鼻を垂らしてるだけで元気だからと、休日にお出かけしたりしていないかなぁ、、?と考えてしまいます。さらに言いますと、、抗生剤飲ませて、お出かけに行くとかはやめてね、、と思ってます。もちろん、どうしても必要なお出かけは仕方ないですけどね。
あい先生のブログから 抗生剤のデメリット①
抗生剤による攻撃を受けると、細菌のほうは「なんとか生き延びよう」とします。
すると「抗生剤に対抗する術」を獲得してしまう菌がでてきます。
このようにして抗生剤が効きにくくなった細菌を耐性菌といいます。
耐性菌ができる要因
・抗生剤を必要ないにもかかわらず使いすぎる
・中途半端に抗生剤を使う
といわれています。
複数の条件が重なって耐性菌が生まれるといわれているので、抗生剤を何回以上使ったらダメというのは決まっていません。
中途半端に抗生剤を使うとダメなのは、生き残った菌が耐性を獲得しやすいといわれているからといわれています。
しかし、この耐性菌、どこか他人事だと思っていませんか?
「私たちの粘膜の表面には常在菌叢がある。
常在菌叢の中には少数派だけれど、病原菌もいる。普段はいい子ぶっているけれど、常在菌同士バランスが崩れると、いい子の仮面がはがれて、私たちに牙をむく。」
という話をしました。
風邪に抗生剤を使い続けるとどうなるでしょう。
そのうち「抗生剤に対抗する術」を身に着け、常在菌が耐性菌になってしまいます。
常在菌叢の中にいる病原菌まで、耐性化した病原菌におきかわってしまうのです。
つまり、自分が持っている常在菌の中に耐性菌がひそんでしまうということです。
風邪をこじらせて細菌感染になる度に、その耐性菌が悪さをすることになります。
すると、どんどん強い抗生剤を使わなくてはならなくなって、さらに耐性化が進みます。
全然他人事ではありません。
抗生剤を多用すると、のちのち自分の首をしめるのです。
いよいよ大病をしたときに、効く抗生剤がない!なんて嫌ではないですか?
だから、私は必要のない時に抗生剤を使うのはさけたいと思っています。
とくに、未来のあるこどもたちには、できるだけ抗生剤を使いたくないと思っています。
鼻風邪・のど風邪のところで、
「ウィルス感染によって常在菌もダメージをうけてしまう。常在菌が元に戻るのに1~2週間かかるので、風邪が治った後も1~2週間は新たな風邪をひきやすい状態になってしまっている。」
とお話をしました。
鼻風邪・のど風邪に抗生剤を使うとどうなるでしょう。
抗生剤は、私たちを守ってくれている大切なバリアである常在菌をやっつけます。
常在菌は細菌ですからね。抗生剤でやられます。
抗生剤を使うと、常在菌はウィルスに荒らされてダメージをくらうだけでなく、抗生剤によるダメージも受けてしまうわけです。ダブルパンチです。
ということは、常在菌が元の状態に戻るのにも時間がかかるということです。
抗生剤を使わなければ1~2週間で元に戻るところ、抗生剤を使うと数週間~数か月かかる、あるいは同じようには戻らない可能性もあるといわれています。
抗生剤を使うと、風邪が治った後、数週間から数か月、新たな風邪をひきやすい状態になってしまうということです。
ウィルス感染には抗生剤は効きません。
ウィルス感染に抗生剤を使うということは、無駄に常在菌だけ弱らせているだけになってしまっている可能性があります。「一応、、、」とか「心配だから、、、」で抗生剤を使うのではなく、なるべく風邪は自力で治した方がいいと思っています。
また、毎月のように風邪をひいて、その度に抗生剤のお世話になっている患者さんがいらっしゃいます。毎月風邪をひくということは、基本的にオーバーワークで体を十分に休め切れていないのだとは思います。ついつい頑張ってしまう頑張り屋さんな方なのでしょう。
ただ、毎回抗生剤を使うということは「風邪→抗生剤→常在菌がダメージうけて風邪をひきやすくなる→風邪→…」の悪循環に陥っている可能性があります。少しゆっくりできそうなときは、抗生剤を飲まずに体をやすめて自力で治すことも、時には必要なんじゃないかな、と思います。
休めないときは、こじらせて細菌感染になるのを予防するために抗生剤に頼るのも仕方がないとは思いますが、抗生剤飲んでいるからといつも通りの生活はしないでほしいんです。夜はなんとなくスマホいじったりとかせず、早く寝る。休日は遠出したりせずに、できれば自宅でゆっくりしてほしいです。
愛先生のブログから 鼻風邪・のど風邪 風邪 ≠ 抗生剤
まずは前回、前々回の復習からです。
この前のブログ読んでいない方は、前の常在菌と細菌・ウイルスのところからまず読んでください。
・風邪の原因はほとんどがウィルス。時々細菌。
・ウィルスは細菌よりも小さく、自力では仲間を増やせない。
・鼻やのどの粘膜の表面には常在菌叢があって、病原体が粘膜に入らないように(私たちが病原体に感染しないように)守ってくれている。
・常在菌は多くが病原性の低い穏やかな菌。少数だが病原性をもつ菌(病原菌)がいい子の顔をしてまじっているが、バランスをとりつつ共生している。
これらをふまえ、「風邪をひいてから治るまで」について説明したいと思います。
①ウィルスに感染
風邪はまず、ウィルスが常在菌叢のバリアをかいくぐって粘膜内に入り込むことから始まります。
ウィルスは細菌より小さいので、バリアをかいくぐりやすいのですね。
バリアをくぐりぬけたウィルスは、私たちの粘膜の細胞に入り込みます。
ウィルスは自力で仲間を増やすことができないので、私たちの細胞の中に入り込んだあと、細胞内の装置を勝手に使って、仲間を増やしていきます。
=ウィルスに感染、です。
細菌は大きくて、常在菌叢のバリアをくぐることができませんので、いきなり細菌感染になることは稀です。
細菌感染はどんな時に起こるのかは次のブログに書きますね。
②風邪症状の出現
私たちの免疫細胞はウィルスと戦うために、まずは炎症物質を出して対抗します。
この炎症物質が鼻の粘膜で炎症を起こすとくしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こします(鼻風邪)。
またのどの粘膜で炎症を起こすとのどが痛いなどの症状を引き起こします(のど風邪)。
③ウィルスをやっつけ、風邪が治る
次に、免疫細胞は、ウィルスをやっつける算段をたてます。
ウィルスの情報を集めて、ウィルスに対する抗体をつくり、つくった抗体でウィルスに感染した細胞を破壊します。
感染した細胞が破壊しつくされたら風邪が治ります。
一晩寝ればずいぶんよくなる風邪、時には数日引きずる風邪があります。
この差はどこからくるのでしょう?
以前同系統のウィルスに感染したことがあると、ウィルスの情報が残っているので対処しやすく早く治ります。一方全く初めてのウィルスだと情報集めに時間がかかってしまって治るのが遅くなります。
また、私たちが風邪をひいたのにもかかわらずちゃんと体を休めていないと、免疫が弱り切っていて抗体をつくるのに時間がかかってしまい治るのが遅くなります。
さて、風邪が治りましたが、まだ「めでたしめでたし」ではありません。←これ大事!
粘膜で炎症が起きたわけですから、常在菌も少なからぬ影響をうけてます。
常在菌が少なくなってしまったり、常在菌層のバランスが崩れて病原菌が優勢になったりします。
時間の経過とともに、徐々に常在菌叢は元の状態に戻っていきます。
それには1~2週間かかるといわれています。
1~2週間は、常在菌によるバリアが弱い状態、つまりまた新たな風邪をひきやすい状態ということです。
常在菌叢が元に戻って、やっと「めでたしめでたし」です。
風邪の原因はほとんどがウィルス。時々細菌。
ということで、前回ウィルス感染による風邪のしくみを説明しました。
簡単に復習です。
ウィルスが常在菌叢のバリアをかいくぐって私たちの粘膜の細胞に入り込む。
↓
ウィルスが仲間を増やす。(つまりウィルスに感染。)
↓
私たちの免疫細胞が炎症物質をだす。(すると風邪症状があらわれる。)
↓
免疫細胞がウィルスに対する抗体をつくり、つくった抗体でウィルスに感染した細胞を破壊する。
↓
感染した細胞が破壊しつくされたら風邪が治る。
(しかし常在菌はまだダメージを受けたまま。ここが細菌感染の原因になります!)
この時の常在菌層の状態 ここ大事!
どんな状態かというと、
・常在菌が少なくなっている。つまりバリアがスカスカ。(→病原菌が入り込む。)
・常在菌同士のバランスがくずれて、病原菌が増えてしまっている。(→私たちに牙をむく。)
↓
1~2週間かけて、常在菌叢が元の状態に戻る
↓
「めでたしめでたし」という流れでした。
細菌による風邪はどんなふうに起こるのでしょう。
ウィルスはとっても小さいので常在菌叢のバリアをかいくぐりやすいですが、細菌はそうはいきません。
常在菌叢がしっかりバリアをしてくれている状態だと、病原菌はそのバリアを越えることがなかなかできないのです。
それではどういうときに細菌が私たちの粘膜に入り込むのか。
まさに、ウィルス感染で常在菌叢がダメージをうけたときです。
常在菌叢がダメージをうけて、常在菌によるバリアが弱くなっているところを狙います。
また、忘れてはいけないのが、もともと常在菌の中にいた病原菌の存在です。
普段はたくさんのおとなしい菌にかこまれていい子のふりをしていますが、ウィルス感染によりバランスが崩れると、病原菌が増えます。すると病原菌のいい子の仮面がはがれてしまいます。いつもは常在菌として私たちをまもってくれている菌が、私たちに牙をむくということです。
細菌による風邪も、ウィルスの時と同じように、鼻水鼻づまり、のどが痛いなどの症状をひきおこしますが、細菌感染はウィルス感染のあとに引き続いておこるだけあって、症状もこじらせた感じになります。
鼻水はウィルス感染のときは白っぽいですが、細菌感染になると黄色から緑色になってドロッとします。
鼻の隣にある副鼻腔にまで炎症がいき、鼻風邪にとどまらず副鼻腔炎になってしまっていることがほとんどです。また、とくにこどもだと、鼻とつながっている耳にも炎症が生き中耳炎になってしまうことがあります。
のどの場合も、とんでもなく痛くてご飯が食べられない、ひどいと水も飲めないような状態になります。
細菌感染も自分の免疫で治すことが大事ですが、こじらせてしまった場合には抗生剤が必要になります
ここ何回かでお話してきましたが、抗生剤は細菌にたいする武器です。
大多数の風邪はウィルス感染によるものなので、抗生剤は効きません。
ですが、「風邪=抗生剤」と思っている方がとても多いです。
抗生剤を処方しないと、患者さんから「抗生剤はでないのですか?」と聞かれることが多いです。
くどいですが、風邪のほとんどがウィルス感染で、抗生剤は効きません。
体を休めて自力で治す必要があります。
けれど、
忙しくて養生できないと、治す力が弱くなって治るのに時間がかかります。
なかなか治らないということは、常在菌叢もずっとダメージをうけたままです。
すると常在菌叢のバリアが低下したままになってしまい、こじらせて細菌感染にもなりやすくなってしまいます。
忙しくてなかなか休めない現代人は、ウィルス感染からもれなく細菌感染になってしまう方が少なくないのです。
何度もクリニックに受診してもらうのも難しいだろうし、細菌感染にこじれるのを予防するために、ウィルス感染の段階でも抗生剤を処方してしまうことがほとんどです。
また、軽症な患者さんに「抗生剤は必要そうではないけれど」とお話することもありますが、たいてい「いや、でも欲しいです」といわれることが多いので、実際は「風邪=抗生剤」で処方しています。
ただ、ずっと「それでいいのか?」という思いがありまして、、
というのも、抗生剤にはデメリットがあります。
デメリットについて、短い診察の間には話しきれないし、かいつまんで話しても全然患者さんに刺さりません。結局「抗生剤ください」とわれてしまいます。
なので、いつかブログにちゃんと書こうと思っていました。
次はやっと、書きたかった抗生剤のデメリットのお話です。
愛先生のブログから 常在菌と細菌・ウイルス
5月末に開催された第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に参加してきました。
ん゛ー、、。勝手に画像が回転したまま戻らない(T_T)。
さて、当院はおかげさまで5月11日に開院3周年を迎えました。
開院当初から「ブログに書きたい」と思っていたテーマがあります。
「抗生剤について」、です。
なかなか重い腰が上がらず、のばしのばしになっていましたが、今年こそ書くぞ!とここで宣言したいと思います。
抗生剤のお話をする前に
・常在菌について
・細菌とウィルスについて
から始めた方がいいかなぁ。どう書いたらわかりやすいかなぁ、、。
いろいろ考えています。
さて、抗生剤についてブログに書くと宣言しましたが、なぜ書こうと思ったのか、です。
風邪の治療には抗生剤と思っていらっしゃることがとても多いのですが、実は大多数の風邪には抗生剤は効きません。
でも、風邪をこじらせると結局抗生剤が必要になることがありますし、何より患者さんからの希望が多いので、風邪には抗生剤を処方しています。
しかし、抗生剤にはメリットもありますが、デメリットもあります。
デメリットについて、短い診察の間に話すことが難しいです。
かいつまんで話しても患者さんには刺さらなくて「でもやっぱり抗生剤を処方してください」といわれてしまいます。
なので、ブログにしっかり書きたいな、と思ったわけです。
いきなりデメリットの話をしてもわかりにくいので、順を追って話していこうと思います。
まずは、ウィルスと細菌の話から始めますね。
鼻風邪やのど風邪、それはたいていウィルスのしわざです。
時々、細菌も悪さをすることがあります。
「ウィルス」と「細菌」。
みなさん、同じようなものだと思っていませんか?
実は全く別の存在で、いろいろ違いがあります。
ここで覚えてほしい違いは3点あります。
①大きさ
②仲間を増やす方法
③治療法
です。
①大きさについて
ウィルスも細菌もどちらも肉眼では見えないくらい小さいですが、ウィルスの方がさらに小さいです。
②仲間を増やす方法について
ウィルスも細菌も仲間を増やして生きていかなければいけません。
しかし、ウィルスは、自力で仲間を増やすことができません。誰かの細胞の中に入って、その細胞が持っている機能を拝借しないと仲間を増やすことができないです。
一方、細菌は自力で仲間を増やすことができます。
③治療法について
風邪の治療には「抗生剤」と思っている方が多いと思います。
しかし、ウィルスが原因の風邪には抗生剤は効きません。インフルエンザウィルスや帯状疱疹ウィルスなど、一部のウィルスには抗ウィルス薬があったり、ワクチンで予防できたりしますが、鼻風邪やのど風邪の原因となる大多数のウィルスをやっつける薬はありません。しっかり養生して自分の免疫で治す必要があります。
細菌が原因の風邪には抗生剤が有効です。
「実は鼻や口の中はバイ菌だらけだ」
なんてことを聞いたことがありませんか?
前回「ウィルスと細菌」の話をしましたが、ここでいうバイ菌とは細菌のことです。
そう、鼻や口の粘膜にはたくさんの細菌がいるんです。
「細菌」というと、、
こういう顔つきのヤツを想像しませんか?
しかし、普段、鼻や口の中にいる細菌はもっと穏やかないいヤツです。
こんな感じ。別人のよう。
みんな仲良く粘膜の表面で暮らしています。
彼らを「常在菌」といいます。
そして粘膜表面で暮らすコミュニティのことを「常在菌叢」といいます。
叢(そう)は、くさむらという意味です。
粘膜の表面でくさむらのように細菌が広がっているのですね。
どんなタイプの細菌が常在菌になるのでしょう。
多くはおとなしい性格の細菌、つまりあまり悪さをしない病原性の低い細菌です。
しかし、一部には病原性を持つ細菌もまじっています。
病原性をもつ細菌は、普段はいい子ちゃんになって、みんなと仲良くしていますが、常在菌同士のバランスが崩れるとトラブルを起こすことがあります。
常在菌はどんな働きをしているでしょう。
感染防御です。
ウィルスや病原菌(悪い細菌)が、ヒトの粘膜に入ってくるのを防いでくれています。
また、私たちの免疫細胞を刺激することで、私たちの防御力を高めてもくれます